+α(プラスアルファ)からの脱却
小学校社会の第6学年の学習では、「キリスト教の伝来、織田・豊臣の天下統一を手掛かりに、戦国の世が統一されたことを理解すること」を内容として取り扱うことになっています。教科書を開いてみると、「戦国の世から天下統一へ」と題した章の冒頭には、2頁見開きで長篠の戦いの絵(長篠合戦図屏風)が掲載され、「長篠の戦いがあったころの世の中は、どのような様子だったのでしょうか」、「屏風絵を見ながら、戦いの様子について話し合いました」と記述されています(東京書籍『新編新しい社会6』歴史編を参照)。
この屏風絵は1575年に起こった長篠の戦い(最近は主戦場である設楽原〈したらがはら〉を加え、長篠・設楽原の戦いと表記するようになってきています)の様子を描いたものです。成立は17世紀後半と言われており、当時の戦場を正確に再現したものではありませんが、他に残された戦記などを踏まえて描かれているとされており、戦国時代の戦(いくさ)の様子を子供たちにイメージしてもらう上で貴重な資料となっています。また、一つの絵に織田信長、羽柴(豊臣)秀吉、徳川家康が描かれていることから、天下統一の流れを押さえる学習にも結びつくため、子供たちの学びを様々に引き出す上で恰好の絵画資料といえます。絵の構図としても、中央の左手に織田信長・徳川家康連合軍、右手に武田勝頼軍を描き、鉄砲隊や馬の侵入を阻むために設置された馬防柵などが目に付く左手に、右側から武田軍の騎馬や長槍を持った兵が向かっていくという対比は、戦の手法の転換を鑑賞側に強く印象付ける描写となっています。
さて、なぜ今回の話題として「長篠合戦図屏風」の話を取り上げたかというと、先週開催された令和7年度(第61回)全国特別支援学校長研究大会(6月26日・27日)で、講師の高橋純先生(東京学芸大学教授)がお話しされた講演「デジタル学習基盤を活かした今後の学校経営」の中で、「長篠・設楽原の戦い」が引き合いに出されていたからです。NHK大河ドラマ「どうする家康」の長篠・設楽原の戦いのシーンで、羽柴秀吉が「もはや兵が強いだけでは戦には勝てん」とつぶやき、一新された戦術を目の当たりにした松平信康(家康の長男)が家康に「父上、これが戦にございますか?」と語りかけるそうです。高橋先生は、わずかな鉄砲使用に留まった武田軍の戦い方を「騎馬隊をより強くするための鉄砲活用」、圧倒的な数の鉄砲を効果的に使用した織田軍の戦い方を「戦いに勝つための鉄砲活用」と整理され、現段階の授業づくりについて「騎馬隊に鉄砲を持たせるようなICT活用をしていないか」と問題提起されました。これまでの一斉指導に見られる授業の在り方を「伝統的な授業」とすると、これに「個別」「協働」「ICT」等の要素を+αした授業はあくまでも「伝統的な授業」を極める発想に留まっており、今後は本質的に授業の在り方を検討し、理念等も新設計した新しい授業、「個別」「協働」「ICT」等の要素が授業に埋め込まれ、授業の形自体も変わるような転換が必要ではないかと話されていました。従来の授業は、教師の指示によるステップバイステップで進む単線型になっているので、今後は子供一人一人が主体性を発揮し、自己判断による進行や必要に応じて教師・仲間と協働するような複線型にしていく必要があるとのことでした。
伝統的な授業からの脱却は、特別支援教育という殻に留まらず、全国で挑戦が始まっている「新しい授業」に目を向け、「専門性の維持・継承」という発想を超える創造力が求められていると強く感じた次第です。
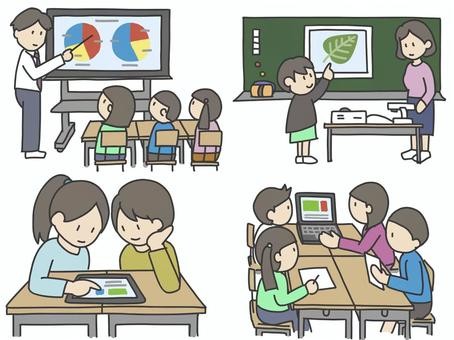
 筑波大学附属桐が丘特別支援学校
筑波大学附属桐が丘特別支援学校